2022年10月6日に刊行された『なるほど図解「一冊目に読みたいDXの教科書」』の出版にあたり、出版のきっかけや苦労話などのエピソードを振り返りたいと思います。
今回は執筆のきっかけについて共有いたします。
誰に届けるために書籍を執筆するのか
書籍はアナログな媒体です。デジタルシフトが加速する今、なぜアナログ媒体で情報発信をしなければならないのでしょうか。その答えはただひとつ──アナログ媒体を通じて情報発信をしなければ、すべての日本人にDXの必要性や本質を伝えられないからです。ブログで情報発信をしても、検索してブログを読む人は日本人全体の一部に過ぎません。YouTubeで講座を配信しても、それを見つけて視聴する人もまた日本人全体の一部に過ぎません。
組織がDXに成功するためには、組織に所属する全員がDXの必要性、DXとは何をすることなのか、DXの難しさを理解しなければなりません。しかし、それらを熟知した組織は存在せず、特に普段デジタル媒体で情報を得ていない方々には知見が届かないのが現状です。
そのため、アナログ媒体としての書籍を通じて、できるだけ多くの日本人にDXを学んでもらうことが必要だと感じました。
何のために書籍を執筆するのか
DXに関する書籍を出版しようと思い立ったのは、DX本が加速度的に増えた2020年ごろです。これらの多くは、以下のいずれかのカテゴリーに分類されます。
- 特定企業の事例にフォーカスした書籍
- 経営戦略の観点から経営者向けに書かれた書籍
- 企業が自社のITサービスを宣伝するための書籍
①のタイプは非常に参考になりますし、現場の大変さが十分に記述されていない場合もありますが、実践知を学ぶうえで役立ちます。しかし、業種や企業規模の違いから自社に当てはめて考えるには課題があったのではないでしょうか。
②のタイプは、DXを経営視点で整理している点で重要ですが、経営学の基礎知識を持たない経営者や一般社員には難解で、自分ごととして捉えにくい部分があったかもしれません。
③のタイプは、一定の技術やサービスについて詳しく記述されているものの、執筆企業の論理に沿っているため読者視点とずれやすいという課題がありました。
結果として、誰にでも理解でき、DXの本質や全体像を体系的に学べる書籍は存在しなかったように感じました。組織を挙げてDXを推進するには、組織全員が共通の理解を持ち、そのうえで自社のあるべき姿を議論しなければ、計画策定の段階でプロジェクトが頓挫しかねません。せっかくDXを始めようという掛け声をかけても、組織全体の理解が一致せずに頓挫するプロジェクトを減らすために、誰にでも理解でき、DXの基礎を体系的に学べる書籍が必要だと強く感じました。
出版の方法にはいくつもの種類がある
実際に「出版したい」と思っても、思い立ったからといってすぐに執筆できるわけではありません。たとえ執筆を開始できても、出版されなければどんどん古いコンテンツになってしまいます。
ネットで出版方法を調べると、主に以下の三つがあることが分かりました。
- 商業出版
- 自費出版
- 協力出版
商業出版は出版社が企画して出版するもので、出版にかかるコストを出版社が負担し、著者は印税を受け取ります。著者が自ら企画を持ち込む例外的なパターンもありますが、順序が変わるだけで役割分担は同じです。よく「書籍を出したら印税生活が待っている」と聞くのはこのタイプです。
自費出版は著者が企画し、自分でコストを負担して出版するものです。著者が売上の大部分を受け取れると推察されますが、販売部数が限られるため、ビジネスというより「自身の思いを知ってもらいたい」「自社のサービスをアピールしたい」といった動機で出版されることがほとんどでしょう。
協力出版は、商業出版と自費出版の折衷で、著者と出版社がコスト負担や責任を一定割合で共有します。
実際に書籍を見ても、どのタイプで出版されたかは分かりにくく、区別がつきにくいのが実情です。
この三つのうち、圧倒的に多くオファーが来るのは自費出版タイプです。実際には自費出版というより出版を通じた企業プロモーションの提案であり、彼らの提案は「出版」そのものではなく、企業やサービスの総合的なプロモーションです。話を聞くと、
「御社は誰にどんな発信をしたいのか? そのためにどんなチャネルを組み合わせるべきか?」
を真剣に尋ねられます。すべて答えると非常に高額な提案ができあがるビジネスモデルです。高額になる理由としては、書籍出版のコストに加え、執筆代行費用、同時並行で実施するイベントやプロモーションの費用、企画費用などが含まれるためです。特に驚くのは「執筆代行費用」が含まれており、忙しい経営者に代わってゴーストライターがすべて企画・執筆してくれるというサービスだという点です。私はDXについて好き勝手に書かれるのは困るため、丁重にお断りしました。
ただし、ホームページの問い合わせフォームからメッセージが届いた段階では、まるで営業出版における執筆依頼のように装っていることも多く、初回コンタクトで見分けるのは難しい場合もあります。有名出版社の名前をかたった企業自費出版の提案も存在します。
SBクリエイティブ社からのコンタクト
出版の経験がある周囲の人に話を聞き、いかに営業出版につなげるかを尋ねたものの、決め手となる情報は得られませんでした。やがて2021年、多くの組織がDXに取り組みDX関連書籍が増える一方で、「DX」というキーワードの検索数は減少に転じました。検索数の減少はDXが下火になったという意味ではなく、むしろより多くの組織が実践段階に移ったことの表れでした。
DXに関する出版のチャンスが一向に訪れないとあきらめ、ブログやYouTube、Udemyなどでの情報発信に集中していた2021年9月、ついにチャンスがめぐってきました。
SBクリエイティブ社の編集者の方からホームページのお問い合わせ欄を通じてメッセージをいただきました。
DXのやさしい入門書を発行する企画があり、執筆いただけないでしょうかでしょうか?でしょうか?
今回こそ自費出版ではないと感じたため、さっそくZoomでお打ち合わせをすることにしました。主旨を伺うと「DX入門者が理解しやすい書籍が存在しないため、それを企画して出版したい」というお話でした。より多くの方にDXを知っていただきたいという弊社の思いと一致したため、その場でご依頼を快諾しました。
先方が私にご連絡くださった理由は、YouTubeの基礎講座をご覧いただき、入門者向け執筆に適任だと感じていただけたためでした。自分の情報発信が役に立っていると実感した瞬間です。
ちなみに、このときから伴走してくださっている編集者の方とは、コロナ禍の影響もあり、いまだに一度も直接お会いしていません。すべてZoomでのお打ち合わせを重ねています。これも時代の流れなのでしょう。
次回のブログでは、どのような進め方で執筆を進めてきたかをご紹介したいと思います。
執筆者:デジタルトランスフォーメーション研究所 代表取締役 DXエバンジェリスト 荒瀬光宏|荒瀬光宏 プロフィール

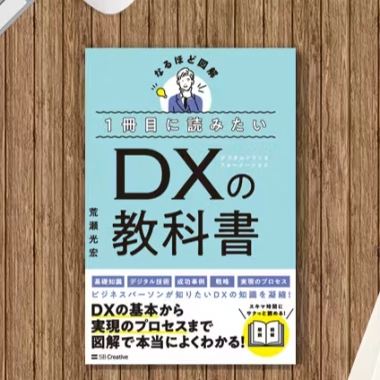



 Warning: Undefined array key 1 in /home/xsdxlabjp/xsdxlabjp.xsrv.jp/public_html/wp-content/themes/genesis_tcd103/widget/tab_post_list.php on line 97
Warning: Undefined array key 1 in /home/xsdxlabjp/xsdxlabjp.xsrv.jp/public_html/wp-content/themes/genesis_tcd103/widget/tab_post_list.php on line 97




コメント